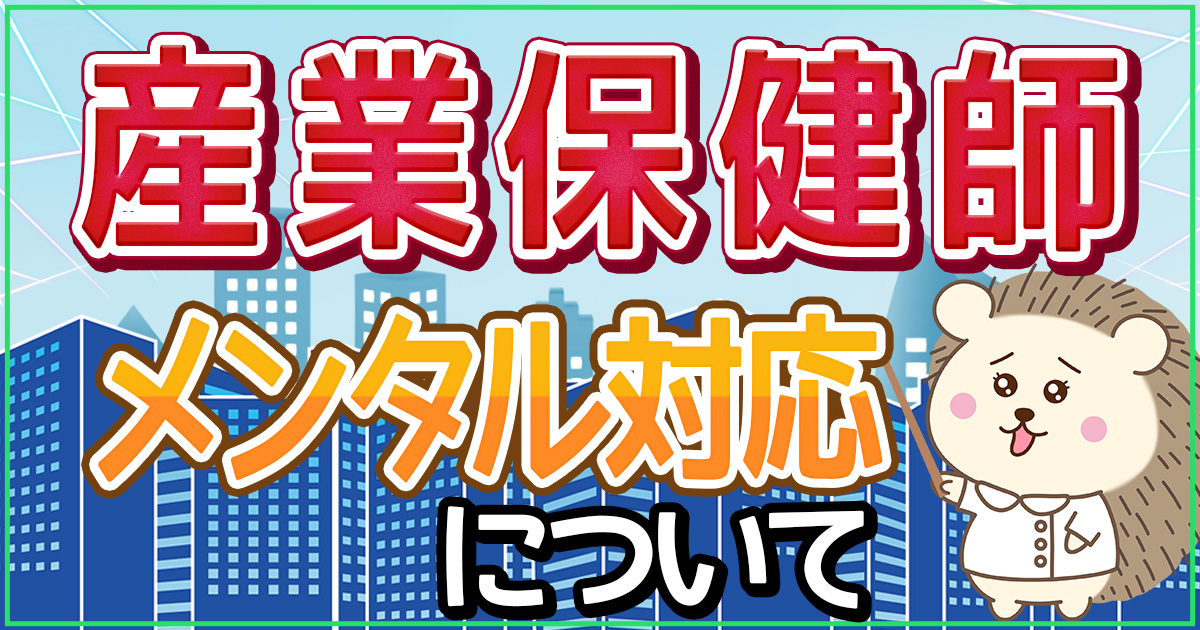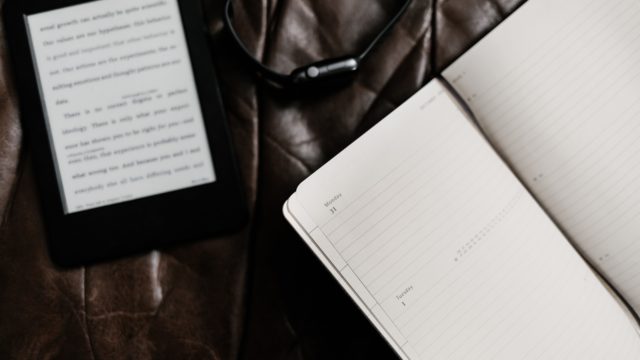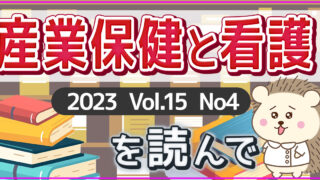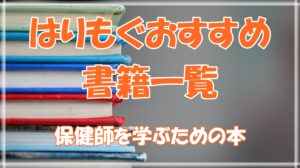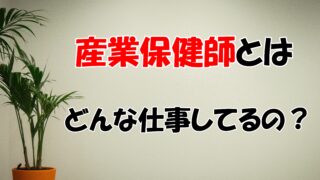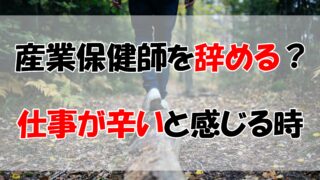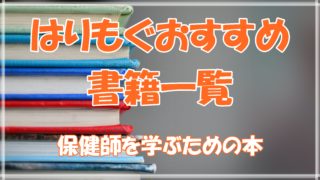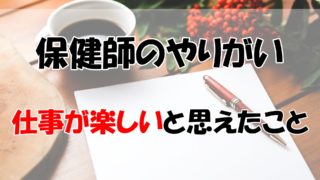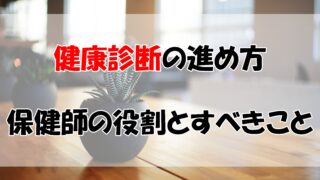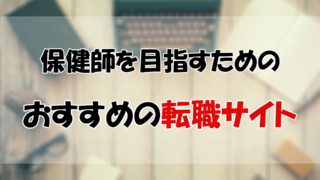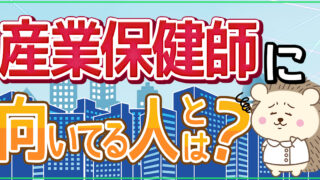産業保健師の役割は、従業員の心身の健康保持増進をサポートする立場です
他部署の上司や従業員から部下や後輩のメンタル不調の相談があった際は対応して適切な対応方法を説明し部署内で解決してもらったり、保健師による面談を実施したり相談内容によっては、必要に応じて産業医との面談や人事部との面談に繋げたりもします
そのため産業保健師は従業員から相談を受けた際、相談内容を理解し適切なフォロー(適切なフォロー者へ繋げる)をすることが大切です
しかし、この判断をすることが難しいと感じる方は少なくないと思います
私自身、産業保健師として働き始めたばかりの時は何でもかんでもメンタル不調者の対応をしてしまい、本来であれば部署内や人事担当者で解決すべき内容も対応しており、従業員の方からも「何かよく分からないけど、メンタル?ぽい人は全て産業保健師にまわせばいいんだよ」と認識されてしまったこともあります
このような状態でメンタル不調者をフォローしていても産業保健師自身が疲れてしまい、適切な対応が困難になってしまうパターンが多いです
また残念なことにメンタル不調者に対して責任を取りたくない、関わったら面倒くさいから関わりたくないなどを理由に産業保健師に全て任せてくる上司も少ないありません
これを認知してしまったら、部署内のラインケアを妨げる行為になると思います
そのため、他部署からメンタル不調者の相談を受けた際は下記の事を気をつけて実施していくようにしました
- 部署内で解決できる内容は、きちんと解決してもらえるようにする
- 相談者のペースに巻き込まれてしまわないように注意するよう指導
- 分からないフォロー対応は、自己判断せずに産業医へアドバイスをもらう
この3点を意識するようになり、従業員のメンタル不調者の対応の認識が少しずつ変わっていったように思います
具体的にどのようなことに気をつけて、実施してきたかについて書いていきたいと思います
部署内で解決できる内容は、きちんと解決してもらえるようにする
現在パワハラという言葉がどんどん増えてきました
なかには本当にパワハラを行っている上司もいますが、残念なことに自分の行動は振り返れらずに何でもかんでもパワハラだ!と自己主張する方もいます
このような方に対して、上司や従業員の方は「本人の考え方の問題って分かっているけど、面倒くさいから関わりたくない」と思い放置してしまうパターンも少なくありません
そして、放置されたことに対して傷つく従業員もいれば注意をされないことをいいことに自分のやっていることは間違っていないんだ!と勘違いしてしまう方もいます
このような方が部署異動で、きちんとラインケアを理解している上司から指導を受けた際、メンタル不調を起こしてしまうことがあります
このような従業員に対して、産業保健師から出来るフォローは少ないように思います
このケースで大切な対応は、上司の部下の管理方法だと思います
管理方法については、産業保健師ではなく人事部や部署の管理職で話し合いをして対応方法について考えるように伝えています
この役割を明確にしていくことが大切だと思います
相談者のペースに巻き込まれてしまわないように注意するよう指導
メンタル不調の部下や後輩、同僚のことを考えて本当に悩んでいるが、どのように対応していいか分からないため産業保健師に相談している従業員もいれば、メンタル不調者にとにかく関わりたくないから全て産業保健師へ丸投げされる方もおられます
産業保健師はメンタル不調者へのフォローはできる場合もありますが、職場でのフォローは必要不可欠となります
そのため、相談者のペースに巻き込まれて全て話を聞いてしまうのではなく役割を1つ1つ明確にしながらフォロー体制について話し合うことが大切だと思います
産業保健師としてラインケア教育やセルフケア教育、面談指導は欠かせない業務の1つだと思います
この部分が手薄だとメンタル不調者は増えてくる一方だと思います
日々の業務に追われて…と悩んでいるのならば業務改善について上司もしくは人事部と話し合いをして方がいいと思います
分からないフォロー対応は、自己判断せずに産業医へアドバイスをもらう
自分で、少しでも疑問や不安になったことに対して「まぁいっか!」と適当な対応をすることが1番よくないことだと思います
分からないことは自己判断せずに、すぐに産業医の先生にアドバイスをもらうようにする
または、職場に保健師の先輩がいる場合は相談するように対応することが大切だと思います
分からないことを適当にせずに1つ1つ丁寧に業務を行なわなければ、何の成長にも繋がらないと思います
相談する人がいないのであれば、産業保健と看護の本を熟読したり産業保健師が集まる学会やコミュニティに参加したり改善方法はいくらでもあります
悩むだけではなく次に行動していくことが大切だと思います
さいごに
近年メンタルやパワハラの基準って、どうなんだろう?と考えさせられるようになってきたと思います
すぐに、メンタルやパワハラと判断しフォローするのではなく話をよく聴いた上で対応することが大切だと思います
メンタルの基準やフォロー方法は、とても難しくフォローした後も「本当にこのようなフォローでよかったのかな?」と悩むことが多いです
しかし、悩んでばかりいても状況は好転するわけではないので少しずつでも成長していけるように努力していきたいと思います