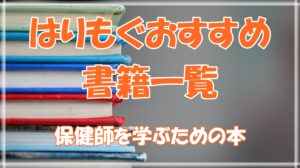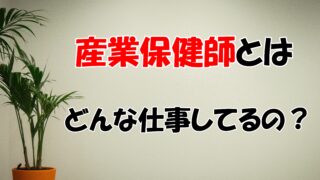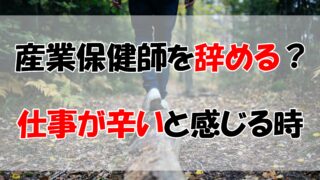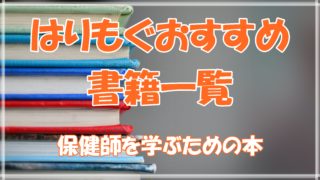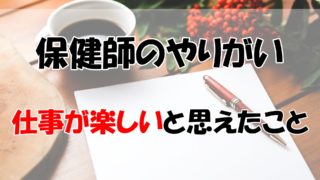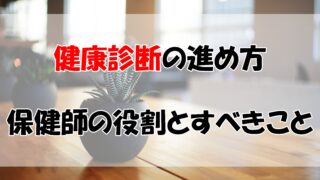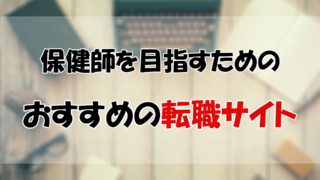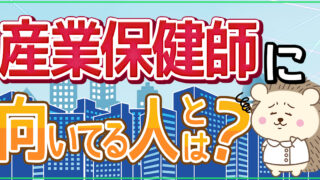産業保健師として働く上で臨床経験は必要なの?と悩む人は多いと思います
実際に産業保健師の募集要項には
【臨床経験1年必須】などの記載がされていることも多いです
産業保健師になり採用面接も何回か担当さしてもらい、
臨床経験が数ヶ月の浅い方や何十年のベテランの方と仕事をしてきて感じたことは
臨床経験は多少は経験をしておいた方が良いと思いますが
臨床経験の長さはあまり重要ではないと感じています
大事なことは、どのような仕事をするか
その人次第だということです
しかし産業保健職は1人職場も産業医が常に勤務しているわけではありません
そのため緊急時にどうすればいいか分からないという状態ではなく
ある程度1人で行動や判断できたほうが
自分自身安心する部分も多いと思います
産業保健師の勤務場所は、工場で働く場合やオフィスで働く場合と様々です
今回は工場とオフィスの両方で産業保健師として勤務してみて
看護知識はもちろん必要ですが、
私がなぜ臨床経験多少必要と感じたかを書いていきたいと思います
工場では救急対応する機会が多い
工場で、働いてる従業員は騒音職場で作業をする方や、
高熱職場で作業をする方や、使用方法を誤ってしまうと
危険を伴う機会を使用する方、有害物質を使用する方など
危険を伴う職場環境が多いです
そのため、ちょっとした切り傷や打撲
出血等の処置は月に数回ありました
止血部位に対してどのように止血するのか、
また傷口に対してどのような処置を行うのが適切なのか、
打撲に対してはどの部位を打撲したのか、
急に頭痛や吐き気がする従業に対して何の疾患を疑い、
それに対してどのような処置が必要なのかの判断を、
臨床経験をもとに緊急性が高いのか低いのか、
病院受診が必要なのかを判断し
従業員に対して適切な処置を行う必要があります
しかし病院とは違い物品が充実しているわけではないので、
軽処置ぐらいの対応しかできません。
中には、工場内に診療所を併設している企業もありますが、
診療所の規模にもより医療行為もできる範囲が限られてきます
工場で産業保健師として勤務していて1〜3年程度の臨床経験は必要だと感じました
オフィスでは救急対応する機会は少ない
オフィスは工場とは違い
危険を伴う作業環境のもとで業務をすることが少ないです
そのため損傷や打撲などの処置は少ないですが、
急に体調不良になる従業員はいます
例えば急に胸痛を訴えたり、頭痛や吐き気
腹痛やめまいを訴えたりするなどの症状がある従業員に対して
どのような処置が適切なのかを判断しなければなりません
実際にオフィスで産業保健師として勤務してみましたが
臨床経験の知識はやはり1〜3年ぐらいは多少は必要だと感じました
臨床経験がない場合は常にイメージをしておくことが大切
上記の内容をみて
「新卒で産業保健師を目指すのはやっぱり理無理なんだ」
と思われる方もいると思いますが、
臨床経験が浅くても緊急事態が起こった場合を想定し、
自分がどのような行動を取ることが必要なのかをイメージして、
緊急対応マニュアルを作成しておくことができれば
臨床経験が少なくとも、対応することが可能になると思います
また、常に産業保健師が緊急時の対応をできるわけではありません
産業保健師も計画休暇や急な休暇がもちろんあります
そのためにも従業員1人1人が動けるような緊急時マニュアルは
作成しておいたほうがいいです
私も臨床経験が決して多い方ではないので緊急対応が必要になった場合は
どのような対応を取るべきなのか、
またどのような判断を瞬時しなければならないのか、
また緊急対応が必要となった部署の所属長には、
どのような動きを取ってもらうのがベストなのかなど、
様々なケースを想定して、産業医や人事部と話し合い
緊急時対応マニュアルを作成していました
また、研修会などに参加し自分に足りてない知識を身につけたり、
研修会で出会ったベテランの産業保健師の方と情報交換をしたりして、
自分が勤務している企業ではどのように活かせるかをイメージしたりしていました
さいごに
産業保健師として働いていて、臨床経験は多少は必要だと感じています
私も臨床経験が浅かったため、たくさん苦労もしてきました
しかし、経験が浅いからと言って落ち込んでいても状況は変わりませんので、
経験不足を補うために何をするべきかを考えて行動を起こすことが大切だと思います
極端な話、臨床経験が未経験でも上記の内容のことをある程度できていれば
緊急時にものすごく困るということは少ないと思います
産業保健師は、企業の中では特殊な業務をしており
少人数で働いていることが多く、
産業保健師だけで解決していくには難しい事例もたくさんあります
そのため人事や総務部、所属長たちとの連携はとても重要となります
臨床経験が浅く苦労することは今でもたくさんあります
しかし経験不足を補うために何ができるかを
常に考えて行動することを怠っていなければ、回避できる問題も多いです
今後も、産業保健師について勉強し経験値を積んでいきたいと思います